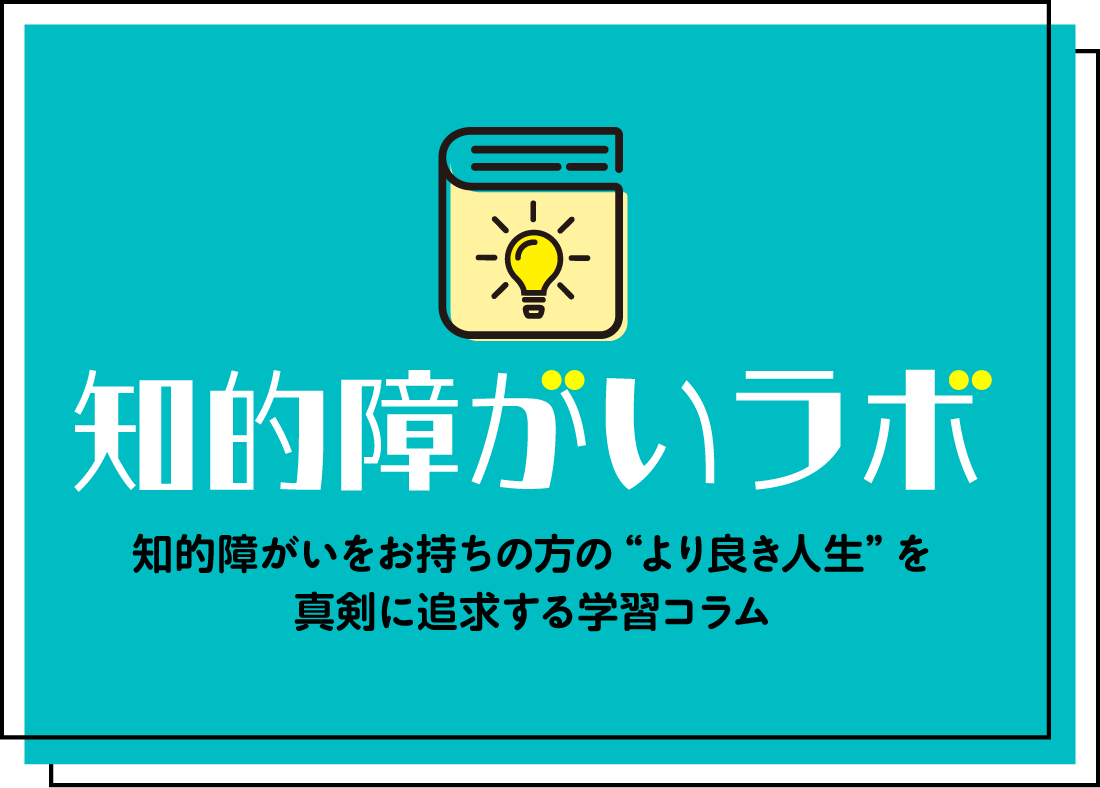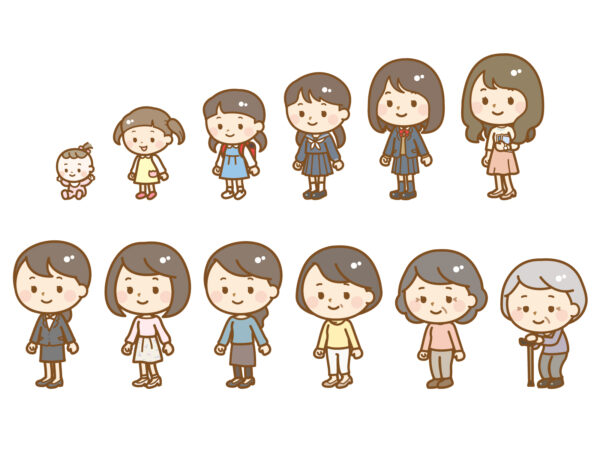今回は、知的障がいをお持ちの方の健康維持のために、私たち就労継続支援B型事業所として日々向き合う中で、どのような取組が出来るのか?を考えてみました。
知的障がいをお持ちの方の健康維持についての現状
的障がいのある方が健康維持に課題を抱えやすい理由はいくつかあります。知的な理解やコミュニケーションの困難さ、生活習慣の影響、環境要因などが関係しています。
1. 健康への理解が難しい 🧠
知的障がいの程度によって、健康に関する情報を理解し、自分で適切な判断をすることが難しいことがあります。
- 食事のバランスが分かりにくい → 好きなものばかり食べてしまう
- 運動の必要性を理解しづらい → 体を動かす機会が減る
- 病気や体調の変化に気づきにくい → 早期発見・予防が難しい
📌 支援のポイント
✅ イラストや写真を使って、健康的な生活習慣を視覚的に伝える
✅ 健康チェック表を作り、毎日の体調を記録する
2. 生活リズムが乱れやすい ⏰
規則正しい生活を送ることが難しく、不規則な生活が健康に影響を与えることがあります。
- 夜更かししてしまう → 睡眠不足で体調を崩しやすい
- 決まった時間に食事をとれない → 栄養が偏り、肥満や低栄養につながる
- 運動の習慣がない → 体力が低下し、生活習慣病のリスクが高まる
📌 支援のポイント
✅ 決まった時間に食事・運動・睡眠をとる習慣をつける
✅ スケジュール表やアラームを活用し、時間を意識しやすくする
3. 体調不良を伝えることが難しい 🗣️
言葉でうまく説明できないため、体調が悪くても周囲に伝えられず、病気の発見が遅れることがあります。
- 「お腹が痛い」「頭が重い」などの症状を言えない
- 歯が痛くても我慢してしまい、虫歯が悪化する
- ストレスや不安があっても表現できないため、心身の不調につながる
📌 支援のポイント
✅ 表情や行動の変化を観察し、小さな異変に気づく
✅ 絵カードやジェスチャーを使い、体調を伝える練習をする
4. 医療機関の受診が難しい 🏥
病院や歯医者に行くことに不安を感じたり、医師の説明が理解しにくかったりして、適切な治療を受けるのが難しい場合があります。
- 診察が怖くて拒否してしまう
- 検査や治療の意味を理解しにくい
- 薬の飲み方や副作用について把握できない
📌 支援のポイント
✅ 事前に病院の流れを説明し、安心感を持たせる
✅ 服薬のサポートを行い、飲み忘れを防ぐ(カレンダーやアラームの活用)
5. 食生活の偏り 🍔
知的障がいのある方は、食べ物の好みが偏りやすく、栄養バランスが崩れることがあります。
- 同じものばかり食べる(好きなもの・甘いもの・揚げ物中心)
- 野菜や魚が苦手で食べない
- 食事の時間が不規則になりがち
📌 支援のポイント
✅ 食べられる範囲で少しずつ健康的な食材を取り入れる
✅ 楽しい雰囲気で食事をし、興味を持たせる
6. ストレスや不安が健康に影響する 😣
環境の変化や対人関係の悩みがストレスとなり、体調不良につながることがあります。
- ストレスで食べすぎたり、逆に食欲がなくなったりする
- 不安が強く、寝つきが悪くなる
- 気持ちを表現できずにイライラしてしまう
📌 支援のポイント
✅ 落ち着ける環境を作る(安心できる場所やルーチンを整える)
✅ 気持ちを表現しやすい方法(絵カード・日記・ジェスチャーなど)を取り入れる
✅ ストレス発散できる活動(散歩、音楽、アートなど)を一緒に行う
まとめ
知的障がいのある方が健康維持に課題を抱えやすい理由は、
✔ 健康への理解が難しい
✔ 生活リズムが乱れやすい
✔ 体調不良を伝えるのが難しい
✔ 医療機関の受診が苦手
✔ 食生活の偏り
✔ ストレスの影響
といった要因が関係しています。支援者は、視覚的に分かりやすく伝える・習慣を作る・安心できる環境を整える ことを意識することで、健康維持をサポートできます!
知的障がいのある方の健康維持をサポートするには、身体的・精神的・社会的な側面からのアプローチが重要です。
支援者ができること
1. 生活習慣のサポート
- バランスの良い食事 🍎🥦
- 視覚的に分かりやすい食事バランスの工夫(例:写真やイラストを活用)
- 一緒に料理をして、食への興味を持ってもらう
- 運動習慣の促進 🚶♂️🎾
- 一緒に楽しく体を動かせる活動(散歩、ダンス、スポーツなど)
- ゲーム感覚で運動できるアプリや道具の活用
2. 健康管理と医療支援
- 定期的な健康チェック 🏥
- 病院や歯科検診のスケジュール管理
- 医師の説明を分かりやすく伝えるサポート
- 服薬管理 💊
- 飲み忘れ防止の工夫(アラームやチェックシートの活用)
- 本人の理解度に応じた説明と練習
3. メンタルヘルスのケア
- 安心できる環境作り 🏡
- ルーチンを作り、生活のリズムを整える
- ストレスが溜まったときのリラックス方法を一緒に見つける
- コミュニケーションの工夫 🗣️
- 気持ちを表現しやすい方法(絵カード、ジェスチャー、アプリなど)を活用
- できたことをしっかり褒めて自己肯定感を高める
4. 社会参加のサポート
- 地域活動やレクリエーションの参加 🎭
- 興味に合った活動を見つけ、一緒に参加をサポート
- 社会的なつながりを増やして孤立を防ぐ
- 仕事や日中活動の支援 💼
- できることを活かせる場を見つける
- 働くことへの理解を深め、達成感を得られるようにする
生活習慣のサポートについて、知的障がいのある方に分かりやすく伝え、楽しく続けられる方法を紹介します。
1. 食事のサポート 🍽️
健康的な食生活を身につけるために
🟢 工夫ポイント
✅ 視覚的に分かりやすく
- 「赤・黄・緑」の3色で栄養バランスを説明する
- 赤(タンパク質):肉・魚・卵・豆など
- 黄(エネルギー源):ご飯・パン・麺・いも類
- 緑(ビタミン・ミネラル):野菜・果物
✅ 食事の見本を写真やイラストで示す
- 1食分の理想的な食事を画像で見せると理解しやすい
✅ 食事の時間を決めて、習慣化する
- 例えば、朝7時・昼12時・夜18時など決まった時間に食べる
✅ 一緒に買い物や調理をする
- 「今日の野菜を選んでね!」と声をかけて、食に興味を持ってもらう
✅ 食べることを楽しむ
- 「カラフルなご飯にしよう!」など、ゲーム感覚で楽しく
2. 運動のサポート 🏃♂️
運動を習慣化するには、「楽しく、無理なく」
🟢 工夫ポイント
✅ 好きな遊びや活動を見つける
- 散歩、ダンス、ボール遊び、なわとび、ヨガなど、本人が楽しめるものを選ぶ
✅ 短時間でもOK!小さく始める
- いきなり長時間は難しいので、「1日10分」から始める
✅ 音楽や映像を使って楽しく
- 音楽に合わせて体を動かす
- YouTubeの簡単な体操動画を一緒に見る
✅ 生活の中で自然に運動を取り入れる
- 買い物に行くときは歩く
- 掃除や洗濯を一緒にする(体を動かす機会になる)
✅ できたことを褒める
- 「すごいね!今日は10分歩けたね!」と具体的に褒める
3. 睡眠のサポート 🛏️
良い睡眠をとるための習慣を作ること
🟢 工夫ポイント
✅ 寝る時間・起きる時間を決める
- 例:「夜10時に寝る」「朝7時に起きる」など、毎日同じ時間にする
✅ 寝る前のリラックスタイムを作る
- お風呂に入る、ゆっくり音楽を聴く、読書をする
✅ 寝る前にスマホやテレビを見すぎない
- 「寝る30分前には画面を見ないようにする」と決める
✅ 快適な寝室環境を整える
- 暗くする、静かにする、暑すぎず寒すぎないように調整する
✅ 昼間に適度に体を動かす
- 適度な運動をすると、夜にぐっすり眠れる
4. 生活リズムを整えるための工夫 ⏳
毎日の生活をスムーズにするために、リズムを作るのが大切です。
🟢 工夫ポイント
✅ 1日のスケジュールを決める
- 朝起きる → 朝ごはん → 運動 → 昼ごはん → お出かけ → 夜ごはん → お風呂 → 寝る
- スケジュール表を作る(イラスト・写真を使うと分かりやすい)
✅ できたことに○をつけるチェック表を作る
- 「朝ごはんを食べた?✅」「お散歩した?✅」など、達成感を感じられる
✅ アラームやタイマーを活用する
- 食事の時間、寝る時間などをアラームで知らせる
✅ 無理なく少しずつ習慣にする
- いきなり完璧を目指さず、「できたらOK!」とする
まとめ
🔹 食事 → 視覚的に分かりやすく、楽しく食べる
🔹 運動 → 楽しく、短時間から始める
🔹 睡眠 → 生活リズムを整えて、快適な環境を作る
🔹 生活習慣全体 → スケジュールやチェック表で習慣化こうした工夫を続けることで、知的障がいのある方の健康をサポートしていきたいと思います。
就労継続支援B型事業所 JOTワークラボ神戸 では、お昼ご飯に、あったかい”具沢山みそ汁”と、出来立ての”おむすび”の提供を始めました🍙🍙😋✨!!
メンバーさんの栄養状態や健康にお役立て頂きたいと願っております!
また、なにより、食べる喜び、楽しみを一緒に分かち合いたいと思っております☆調理については、お料理大好き、食べること大好きな調理師資格を持つスタッフが管理栄養士さん監修の元、毎日違う具沢山みそ汁をつくります☺️
栄養も愛情もたっぷり入った具沢山みそ汁とおむすびを美味しくいただいて下さい🍀*