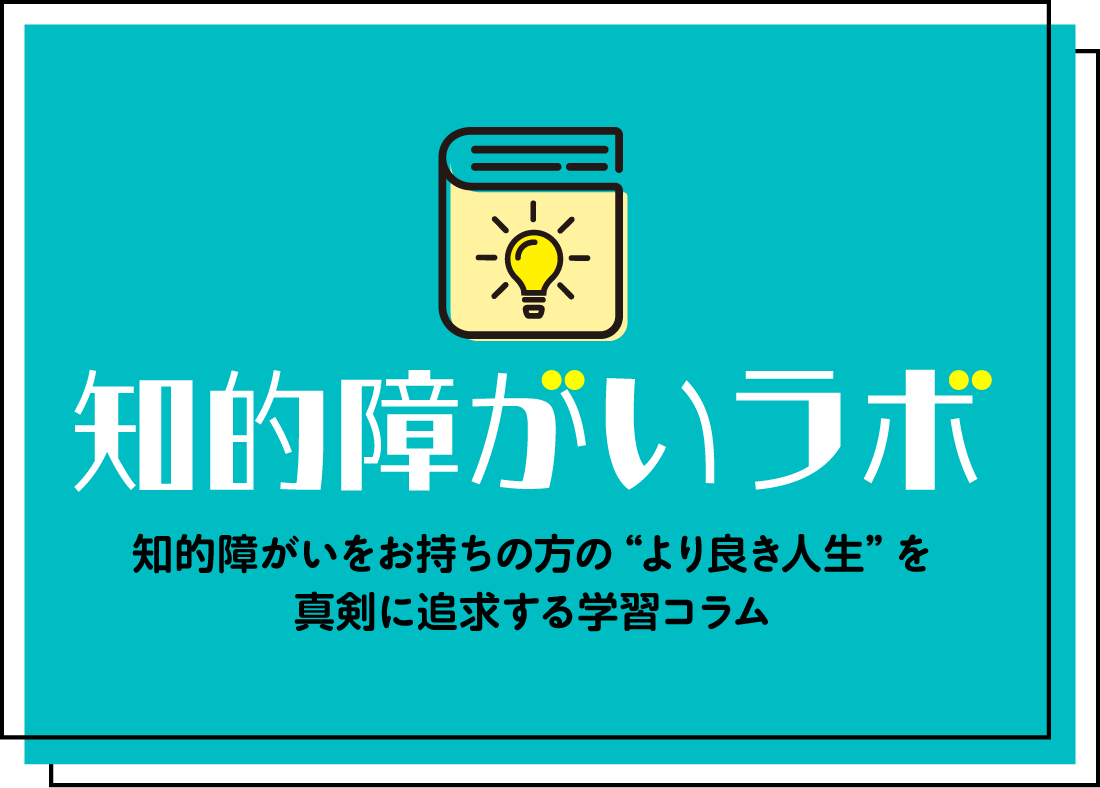「親亡き後」支援に関すること ≪成年後見人制度≫について
知的障がいのあるお子さんを持つ親御さんにとって、「親なき後」という言葉は重く心に響くものです。
愛する我が子の将来を思うとき、「自分がいなくなった後、この子は一人でやっていけるだろうか」「誰がこの子を支えてくれるのだろうか」という不安が胸をよぎることは、決して珍しいことではありません。
この不安は、親としての深い愛情の表れでもありますが、同時に一人で抱え込むには重すぎる悩みでもあります。
しかし、適切な準備と情報があれば、この不安を少しずつ安心に変えていくことができるのです。今回は、知的障がいのあるお子さんの「親なき後」について、具体的な備えや制度、そして何より大切な心構えについて、一緒に考えていきたいと思います。
今回は、成年後見人制度について神戸しおさい法律事務所の弁護士秋山侑平先生にQ&A方式にて質問をさせていただきました。
Q1 知的障がいのあるお子さんの場合、法定後見と任意後見のどちらが適していますか?それはなぜですか?
多くのケースでは法定後見制度が適していることが多いです。
なぜなら、任意後見は本人が自分の意思で後見人を選び、契約内容を決定するものですが、これには一定の判断能力が必要です。知的障がいのあるお子さんは、特に障がいの程度が重い場合、任意後見契約を結ぶための十分な判断能力を持っていないことが多いといえます。
また、軽度の障害の場合には、任意後見を利用することも不可能ではありませんが、自分で選んだ後見人が実際に後見人として実働し始めるのは、判断能力を完全に失った後であり、障害を持つお子さんの老後である可能性もあります。
一方、法定後見制度はお子さん本人の判断能力が不十分な場合に、親族等が家庭裁判所に申立てをすることで利用できます。また、軽度の障害の場合にも、医師の診断があれば、すぐに職務を始めてもらうこともできます(ただし、軽度の障害の場合にはお子さん本人の同意がなければ、後見人が本人に変わって財産を管理した
り契約をすることはできないことに注意が必要です。)
Q2. 親が元気なうちに、後見制度の準備を始めるべき具体的な年齢や時期はありますか?
準備を始めるのに「遅すぎる」ということはありません。
しかし、親がまだ健康で判断能力が十分なうちに準備を始めることが重要です。
具体的には以下のタイミングが適切です
1 お子さんが成人(20歳)を迎える前後
2 親が50代から60代に入ったとき
3 親の健康状態に変化が見られ始めたとき
なお、法定後見の場合、後見人の選任手続きには一定の時間がかかるため(通常3ヶ月程度)、急な状況の変化に備えて余裕をもって準備しておくことが賢明です。
Q3. 親族後見人と専門職後見人、それぞれのメリット・デメリットを教えてください。
①親族後見人のメリット
お子さんのことをよく理解しており、生活歴や好みを把握している
愛情を基盤とした支援が期待できる
費用負担が比較的少ない
②親族後見人のデメリット
法律や福祉制度の知識が不足していることがある
家族間の利害対立が生じる可能性がある
高齢化や健康問題で長期的な支援が難しくなることがある
お子さん名義の預貯金が多額である場合や、お子さんが親や親族の相続手続
が必要になった場合には、家裁から親族後見人を認めてもらえない。
③専門職後見人のメリット
法律や福祉制度に関する専門知識がある
客観的な立場から本人の利益を考えられる
本人の障害にわたる継続的な支援体制が期待できる
④専門職後見人のデメリット
本人との関係構築に時間がかかることがある
報酬(原則、月額2万円~)が発生するため経済的負担がある。
ただし、お子さん名義の財産がほとんどない場合には、市が報酬を支払ってくれる可能性がある。
業務時間に限りがあるため、きめ細かい生活支援は困難な場合が多い。
Q4. きょうだいが後見人になる場合の法的リスクと対処法は何ですか?
1 きょうだいであるがゆえに、客観的に見て本人の利益を図らなければいけないという後見人の立場を全うしにくい。(「きょうだいだから、許される」と考えて不適切な行為に及ぶリスク)
2 親の相続手続が必要な際、きょうだいも相続人になるため、本人の利益よりも自分を優先するリスクがあり、法律上、本人の代わりに相続手続を取ることが許されず、別の後見人を立てなければならなくなる。
3 長期にわたる負担による関係悪化
対処法
1複数後見人又は監督人の選任
きょうだいと専門職の複数後見人を選任し、役割分担するか、または、きょうだいが一人で後見人の役割を担う場合に監督人として専門職を選任してもらう。家庭裁判所に申し立てる際、このような要望をすることで、実行できる。
2 後見人に全てを任せることなく、支援者を複数関わらせ、ケース会議などで、定期的に情報共有し、後見人が不適切な関わりをしていないか確認できるようにする。
【財産管理と法的準備】
Q5. 親の財産を障がいのある子どもに確実に残すための、法的に有効な方法は何ですか?
以下の①~③を組み合わせることが有効です。
①遺言の作成:
最も基本的かつ重要な方法は、明確な遺言を残すことです。
遺言により、障がいのあるお子さんに財産を全て相続させることもできますし、一部の特定の財産を相続させることができます。遺言がない場合は法定相続分に従って分割されるため、必ずしもお子さんの需要に応じた分配にならない可能性があります。
②生命保険や信託の活用:
現預金を遺言等で相続させるだけだと、一括でお子さんが現預金を持つことになり
、お子さんが適切に管理できない場合もあります。
一方、生命保険の中には、分割で支払われるようにすることができる商品もあります。
また、信託により、親族の誰かに親の財産を託し、指示した通りにお子さんに支払わせるということもできます。親族の監督役として弁護士などの専門家を設定することも可能です。
これらの制度制度を活用することで、確実に財産を残しやすくなります。
③成年後見制度の活用:
お子さんに受け継がせた財産が、適切に管理されるには、成年後見人を選任してお
くことが確実な方法です。
遺言と相続対策
Q6. 知的障がいのあるお子さんがいる場合、遺言書に必ず記載すべき内容は何ですか?
以下の事項を記載しておくべきです。ただし、内容によっては、ご自身で正確な記載をすることが困難な場合がありますので、弁護士等の専門家に依頼するのが確実です。
また、遺言作成にあたっては、ご自身で書く自筆証書遺言よりも公証役場で専門家である公証人が作る公正証書遺言の方式で作成するのが望ましいです。自筆証書遺言では、死後に裁判所での遺言確認手続(「検認」といいます。)が必要になりますし、書き間違い等により無効になるリスクがあります。
1 どの財産を誰に取得すべきか、記載しておく必要があります。
その際、どの財産を誰が取得するか、不明確にならないよう注意する必要があります。
例えば、「全財産のうち、●●に4分の3、●●の兄に4分の1を相続させる」という内容では、具体的に××銀行の預金はどちらが取得するのか、自宅の土地建物はどちらが取得するのかが読み取れないので、不適切です。
2 自筆証書遺言の場合には、全文を必ず直筆で書く必要があります。
また、遺言を残される方の氏名と、作成日付を記載し、印鑑を押す必要があります。印鑑は法律上は実印でなくともかまいませんが、本人の印鑑であることを証明しやすいため、実印の方が望ましいです。
3 必ず記載すべきとまでは言えませんが、遺言の通り、確実に手続を取ってもらえるようにするため、「遺言執行者」を指定しておくことが望ましいです。
例えば、障害のあるお子さんのきょうだいを遺言執行者にしておけば、そのきょうだいのみで銀行等での相続手続きを取ることが可能となり、障害を持つお子さんの署名や印鑑は不要となります(きょうだいが遺言に異を唱える可能性がある場合には、弁護士等の第三者を遺言執行者にすることも可能です)。
Q7. 障がいのあるお子さんと他のきょうだいとの間で、公平な相続を実現するための具体的な方法を教えてください。
1 他のきょうだいに遺留分を残しておく
遺言で障害のあるお子さんに多くの財産を残す場合、他の兄弟の遺留分を侵害してしまわないように注意すべきです。遺留分とは、相続人に最低限確保された取り分のことで、遺言で「全財産を●●に」と指定したとしても、遺留分を持つ相続人は、遺留分の分は金銭で返してもらう権利があります(不動産や物で返してもらうことはできません。)。
子どもの遺留分は、法定相続分の半分です。例えば、三兄弟で相続する場合には、1/3×1/2=1/6となります。
きょうだいが、遺留分すら要らないと言ってくれる場合には問題ないのですが、そうでない場合には、少なくとも遺留分相当額はもらえるように相続させると、後にきょうだい間で揉めにくくなります。
2 生前贈与や生命保険の活用
不動産、預貯金等の相続財産をきょうだいの誰かが多く相続することになる場合、生命保険や生前贈与により、他のきょうだいの取得額を調整し、公平を図ることも考えられます。
3 事前の説明、意向確認
きょうだい仲が悪くない場合には、お子さん方の意向を確認しておき、障害のある子に多く残すとすれば、その点につき説明してきょうだいの理解を得ておくことが考えられます。また、きょうだいが相続について具体的な意向をお持ちの場合には、それを踏まえて遺言を作成したり生前贈与をしておくなどして調整し、公平感を持たせることが考えられます。
Q8. 成年後見制度を利用していても生じうる法的トラブルとその予防策について教えてください。
質問事項4でのご回答と同様となりますが、
①成年後見人のミスマッチにより、財産の不適切な管理や横領、障害支援の知識不足による不適切支援や障害者虐待の危険があります。
予防策としては、後見人を選任する段階で、家庭裁判所に、どのような後見人が適切か、要望をしっかりと伝えておくことが重要です。また、質問事項4、9で述べた通り、複数後見人又は監督人の選任、複数の支援者による情報共有も有効です。
②成年後見人がいたとしても、障害を持つお子さんが急にパニックを起こすなどして、第三者を傷つける、物を壊すなどして損害を与えてしまうことがあり得ます。
このような場合に備えて、賠償金をカバーするための保険に加入しておくことが考えられます。
【実際の事例】
事例1 統合失調症・自閉症のお子さん(30代)と自宅で同居していた母親に末期がんが発覚したため、急いで遺言作成や施設探しをしなければならなくなった事例。
お子さんは、兄と仲が悪かったため、兄との同居や積極的な支援は期待できませんでした。また、お子さんには浪費癖があったため、母親の多額の財産を受け継がせたことによる浪費も考えられました。
兄が不満を抱かないよう公平に相続させるような遺言作成や、母親死亡後の財産管理を依頼する成年後見人選任などの手続きを進める必要があり、病の中、母は遺言作成手続、施設探し、後見人選任手続を進めなければなりませんでした。
遺言は亡くなる3日前に作成しましたが、後見人の選任は間に合いませんでした。母が亡くなった後、お子さんは一人暮らしを希望したため、兄は住居を用意するところまでは面倒を見ましたが、その後に環境の変化により妄想が悪化し、家を退去してしまいました。その後、兄が別の施設を見つけ、入所することができましたが、成年後見人は、選任されていないままです。
公正証書遺言を作成し、遺言執行者を兄に指定しておいたおかげで、相続手続は兄が主導で進めることができ、決められた相続分をお子さんも受け取ることができました。その後、兄は本人と連絡を取っていません。
事例2 親亡き後、親族が全財産を相続した上、障害のあるお子さんに金銭を要求してきた事例。
重度の統合失調症のお子さん(50代)は、母親(80代)と自宅で同居し、B型就労を利用していました。いざというときのためにお子さんのいとこ(母の甥)が成年後見人として選任されていましたが、普段のお子さんの面倒や支援者とのやり取りは母が専ら担っていました。
しかし、母が病気になり亡くなってしまい、お子さんは一人で自宅で生活することになりました。
その後、後見人となっているお子さんのいとこが調べたところ、母がお子さんのおば(母の姉)に「私がお子さんの面倒を見るから」と言われ、全財産をおばに渡す内容の遺言を作成していたことがわかりました。そして、おばは、後見人(いとこ)に対し、「●●(本人)がギャンブルにはまったことにして、本人からお金を出させなさい」と金銭を要求してくるようになりました。
その後、親族後見人(いとこ)が家庭裁判所に事情を報告し、弁護士の後見人をもう一人追加することになり、弁護士後見人が本人の預金を管理しておばの要求を拒否しました。また、おばに対し、遺留分を請求し、支払わせることができました。もともと、親族後見人とおばとの関係は悪く、当初から、弁護士後見人を選任しておくべき事案だったといえます。
事例3 障害のあるお子さんの財産を、親族が不当に使用した事例
知的障害を持つお子さん(30代)の親が死亡し、親名義の不動産をお子さんとその兄が2人で相続しました。兄は、お子さんの唯一の家族でしたが、施設に入所させた後はほとんど関わることがありませんでした。
そればかりか、兄は、お子さんにも2分の1の持分権がある不動産について、お子さんに無断で担保に入れてローンを借り入れたり、お子さんが受け取る障害年金を自分のために使わせようとするなど、お子さんの財産を不当に使用させようとしました。
その事例は、問題が発生してからずいぶん時間がたった後に、市が後見人の選任手続を取り、後見人が財産を管理することで、兄から財産を守ることができました。
もっとも、本人と兄との関係性を踏まえ、親の生前のうちに、後見人を付けておくべき事案でした。